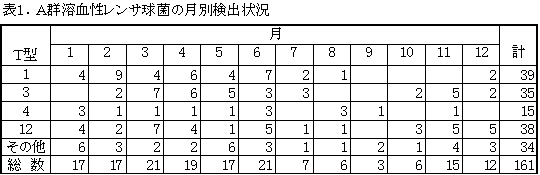A群溶血性レンサ球菌・小児科定点における菌の分離状況について(第23巻、12号)
2002年12月
溶血性レンサ球菌は、化膿レンサ球菌、口腔レンサ球菌、およびその他のレンサ球菌に大別できる。また血液寒天培地上の溶血性により、α溶血、β溶血、非溶血(γ溶血)がある。α溶血は不完全な溶血で菌の集落周辺に緑色帯(メトヘモグロビン)を生じ、β溶血は集落周辺の血液を完全に溶血するものである。
β溶血の菌株は化膿レンサ球菌と呼ばれLancefieldの血清学的分類でA,B,C,G,L群等に属する菌株が含まれる。β溶血性レンサ球菌はヒトや動物に病原性を示すため、古くから医学、歯学、獣医学の分野で重要視されてきた。この中で最も重要な菌種は、A群溶血性レンサ球菌(S.pyogenes)で、しばしば咽頭に常在し、ウイルス感染による気道の線毛および粘膜の損傷が誘引となって扁頭炎、気管支肺炎を起こす。日常よく見られる疾患として急性咽頭炎、膿痂疹、蜂巣織炎、あるいは特殊な病型として猩紅熱がある。
我が国では、猩紅熱は小児の疾患として代表的なものであったが、化学療法の出現により、重篤な臨床症状を示す定型的な患者発生は少なくなり、今日ではレンサ球菌感染症として扱われている。しかし現在でも扁桃炎、猩紅熱の一次感染症に伴って病巣感染を形成し、その続発症としてリウマチ熱および急性糸球体腎炎を引き起す症例なども散見される。これら以外にも中耳炎、肺炎、化膿性関節炎、骨髄炎、髄膜炎などの他、皮膚化膿性疾患の病因菌として、重要な病原菌の一つである。また本菌は丹毒、産褥熱を敗血症に移行させ、死の転帰をとる重篤な感染症の病因菌でもあるなど、多彩な臨床症状を引き起こしている。
A群溶血性レンサ球菌のほとんどは、主な細胞表層蛋白抗原としてMとT蛋白を有しており、これらの抗原性により型別を行う。 また、この菌は溶血毒素、発熱毒素(発赤毒素)、核酸分解酵素、streptokinaseなどを産生する。
東京都における感染症発生動向調査では、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(溶レン菌感染症)は、小児科・内科の定点より報告が行われている。2002年の溶レン菌感染症は1定点あたりの報告を見ると(26.59人/定点)と2001年の(20.68人/定点)より報告数が多く、溶レン菌感染症流行の兆しを見せている。
1995年より都内小児科定点4病院の協力により、上気道炎患者咽頭拭い液からA群溶血性レンサ球菌分離を実施し、2定点病院からは病院で分離された菌株が送られてきている。それら菌株について、T型別および発熱性毒素型別を実施している。
2002年に分離され、検査を実施した161株のT型はT-1:型:39株、T-12型:38株、T-3型:35株、T-4型:15株、T-28型:7株などである(表1〜3)。2001年に検査した株数100株に比べ2002年には161株と検査株数が増加した。T型別も2001年は T-4型:23株、T-1型:23株、T-12型:22株、T-3型:5株であったが、2002年にはT-3型が35株(21.7%)と増加が注目された。T-3型については、発熱性毒素(SPE)A+Bを産生する株が35株中25株と、ここ数年分離された発熱性毒素B産生株とは毒素産生性に差が見られ、1994年頃に劇症型溶血性レンサ球菌感染症の原因菌として高頻度に検出された菌株と類似していた。小児科定点病院でのT-3型の増加と同時期に、T-3型による劇症型溶血性レンサ球菌感染症の患者が発生した。この株は、発熱性毒素A+B産生しており、T-3型:発熱性毒素A+B産生株による劇症型レンサ球菌感染症患者の増加が危惧される。また、2002年に分離された株の中に、T型別不能株が5株存在したが、M蛋白遺伝子型別検査により、emm49:1株、emm58: 2株、emm75:1株、emm89:1株と決定された。